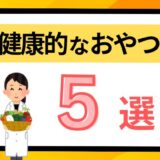「AGE(AGEs)って何?」
「酸化は聞いたことあるけど、糖化って何?」
などの疑問はありませんか?
この記事では、AGEとは何か、AGEを増やさないようにする方法についてお話しします。
目次
AGE(AGEs)とは

AGE(AGEs)とはAdvanced Glycation End Productsの略称で、終末糖化産物と訳され、
食事から摂取した「糖」と体を構成している「たんぱく質」が結合し、変性することで産生される、老化や疲労の原因物質です。
糖化とは、「体の焦げ」と表現されることもあり、老化を促進させるとも言われています。
また、AGEは食後高血糖(糖質の摂りすぎ)により産出されやすくなります。
AGEが産出されやすい環境では、高血糖を抑えるホルモンが過度に働くことで、一時的に低血糖となり、眠気や疲労の原因にもなるとされています。
そして、一度生じたAGEは排泄されにくく、体に蓄積されてしまいます。
気をつけていても、加齢とともに徐々に蓄積してしまいます。
AGEの蓄積が多いグループでは、糖尿病や心臓病の罹患率や死亡リスクが高いことが明らかになっており、他にも歩行速度が遅い、転倒・骨折しやすいなどフレイル状態に至りやすくなるとされています。
健康に生きるためにも、AGEを増やさないように心がけると良いでしょう。
AGEを増やさないようにする方法

糖質の過食を避ける
糖質の過食により、血糖値が高くなってしまいます。
食後高血糖はAGE産生を促すため、避けることがベストです。
糖質源である、主食を1食で大量に食べたり、間食で甘いお菓子を高頻度で食べるなどは控えましょう。
主食はご飯であればお茶碗1杯が適切です。
間食は1日200kcalが推奨されています。
目安で言うと、板チョコ1/2個、プリン1個、クッキー3個程度です。
甘いお菓子が好きな方からすると、現実的な量ではないように思われるかもしれませんが、少しずつ食習慣を変えていけるように心がけましょう。
未精製穀類を選択する
白米や食パンに比べて、玄米や全粒粉パンなどの未精製穀類は血糖値を上げにくいとされています。
また、玄米や全粒粉パンは少し硬いため、よく噛む必要があり、満腹感を得られやすいというメリットもあります。
玄米100%ではお腹が痛くなってしまう場合は、玄米と白米を混ぜて炊くようにしても大丈夫です。
食べる順番に気をつける
食物繊維の多い副菜から先に食べ、次に主菜、最後に主食を食べるようにしましょう。
そうすることで、食物繊維などの効果により血糖値が上がりにくくなります。
「野菜ファースト」を心がけてみてください。
早食いをやめる
早食いには、食べすぎや血糖値が上がりやすいなどのデメリットが多いあります。
早食い傾向のある方は、1口30回は噛むようにして、1食に20分以上はかけるようにしましょう。
かといってダラダラ食べるのもよくありません。1食30分程度が適切な食事時間です。
朝食の欠食を避ける
朝食の欠食により、血糖値が不安定になりやすくなります。
1日3食取ること、食事と食事の間隔を最低でも3時間空けることで、血糖値の推移が安定しやすいです。
朝食の時間が無く食べられていないのではなく、ダイエットのためにあえて朝食を抜いている人もいると思いますが、朝食を食べないことのデメリットも考えて選択するようにしてください。
調理方法に気をつける
AGEは体内で作られる場合が多いですが、約7%は食事からの摂取による蓄積物であるとされています。
食事でAGEを多く含むものが、「高温調理された料理」です。
調理するときは、揚げる・焼く・炒めるなどの高温調理を避け、
生食・蒸す・茹でる・煮るなどの調理方法のほうがAGE量が抑えられます。
禁煙・運動・ストレス・睡眠
昭和大学の山岸教授らの研究によると、
AGE量と生活習慣の関係を調べた研究では、喫煙、運動不足、精神的ストレス、睡眠不足などにより蓄積量が増すことが示されたそうです。
そのため、禁煙・運動習慣の構築・ストレスを溜めすぎないこと・十分な睡眠時間の確保が大切です。
まとめ
AGE(AGEs)について、AGE(AGEs)を増やさないようにする方法についてお話ししました。
食事面に関しては、血糖値との関係が大きいため、これらの方法以外にも食後血糖上昇の抑制が期待できる「お酢」や「カカオポリフェノール」などもAGE対策として有用である可能性が高いです。
AGEは目に見えないため、対策しにくかったり、この方法をやっても結果が見えなくてやめてしまう方もいるかもしれませんが、今回ご紹介した方法はAGEを増やさないという名目以外でも生活習慣において重要な行動ばかりです。
健康の維持・増進のためにも、今回の方法を実践してみると良いでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考
ここまで分かった、老化物質「AGE」の謎と介入戦略(ビヨンドヘルス)
MAGAZINE HOUSE MOOK. ”Tarzan特別編集 疲れ対策の新常識”.マガジンハウス,2023年12月,22~23.30ページ
↑その他にも、呼吸・姿勢・運動・レシピなど多方面から疲れ対策となることについて書かれています。興味のある方はぜひご購入下さい。